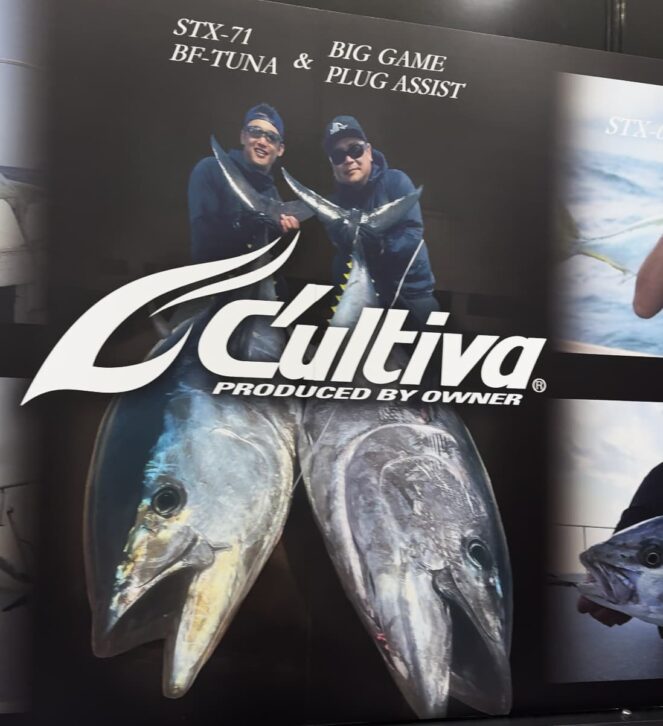連載 平松慶のオフショアワールド vol.10
オフショア講義
北海道サクラマスジギング準備。
人気のサクラマスジギングタックル解説
近年人気の北海道サクラマスジギングは12月下旬頃から始まり、翌6月中旬までの半年間がシーズン。北海道のサクラマスジギングは、太平洋側、日本海側、オホーツク海側と時期をずらしながら楽しめる。北海道サクラマスジギングは、もともとあった北海道伝統釣法から分散化されたものと言えるが、歴史的な話については今回省略させてもらい、現在の北海道の「ジギングスタイル」「必要となるタックル」をお伝えしたいと思う。


その年の天候にもよるが、北海道のサクラマスジギングのシーズンスタート時は、かなり気温が低い中での釣行となる。まず考えなくてはならないのが、その寒さ対策でもある。
サクラマスジギングタックルセレクト
北海道は、広い。その広大な大地を囲むのが、太平洋、日本海、オホーツク海。これだけ広いフィールドを持つ県は、国内では北海道だけであり、エリアを分けて解説が必要になる。
北海道のサクラマスジギングのシーズンは、12月下旬頃から6月中旬。最初に始まるのが太平洋エリア。苫小牧、白老を中心とした地域は1月、2月がシーズンだ。そして2月中旬頃から太平洋エリアと重なるように、日本海エリアでもサクラマスが釣れ始め、2月下旬からがピークとなる。そして4月中旬頃になると、オホーツク海エリアが楽しくなってくる。宗谷岬からのオホーツク海エリアは、少しずつ海水温が緩んでくると、遡上を意識したサクラマスが産卵を意識して岸近くに寄ってくる。流氷がロシア・樺太方面に戻り出すのが3月下旬から4月。これが過ぎるとオホーツク海エリアのサクラマスジギング開幕となる。今回は、初心者にも分かりやすい、まさにこれから始まるオホーツク海エリアのタックルセレクトと狙い方を解説していきたい。
タックルセレクト
ロッド
6フィート前後のあまり張りの無いライトタイプのジギングロッド。
リール
ベイトリールは、小型サイズでPE1号前後が150m程度入るキャパシティサイズでよい。サクラマスジギングは、棚(層)取りが必要になる場面があるので、カウンター付きのベイトリールだと、棚が合わせやすい。PEラインのカラーで水深をカウント出来るが、初心者は、カウンターが付いていた方が釣りやすいだろう。スピニングリールも、PEライン1号前後が150mも巻ければ使える。サイズ的には、湖で使うトラウト用リールのサイズが適合。

ライトジギング対応として発売されているベイトリールが基本。カンター付きが棚が把握しやすくお勧め。遠征でチャレンジする人なら、タチウオやタイラバ用としてすでに持っているもので対応可能だ。

6フィート前後の長さのロッドが使いやすい。張りが強くなく、サクラマスの突然の動きに合わせて曲がってくれるモデルのほうがバレが少ない。
ライン&リーダー
ベイトリール、スピニングリールともにPEライン1号前後。慣れてきたら、より繊細にジグのバイトを得たり、沈下を早めるために、強度(号数)を落として楽しめられるが、1号を基準にすれば釣りは成立する。リーダーはフロロカーボンがベスト。5号クラス(16~20ポンド)が良いだろう。

リーダーとPEラインの結束は、摩擦系のノットでしっかりと結ぶこと。PEラインは1号が平均的な太さだ。
メタルジグ
水深(狙う層)にもよるが、ジグは150g前後が主流になっている。ただ、私の経験上あまり重いジグで探ると、メタルジグのアクションにメリハリが付けにくくなるので、使いやすさを優先すると120~130gがオホーツク海エリアでは良いと思っている。狙う層(水深)が浅いので、潮の流れが強くない限り、ジグウエイトはなるべく軽めが操作しすい。太平洋側のように、水深100mなどの深場を狙う場合は、重さが必要になるが、日本海側の積丹半島エリアでも感じたのは、水温が上昇してくると、狙う層が上がってくるということ。棚さえ把握できれば釣りが成立するので、オホーツク海エリアでの組み立ては、先に挙げた120~130gをお勧めする。

ジグは、軽いほうが動きのメリハリが効いて良いが、あまりに軽いのは他のアングラーの迷惑にもなるので、120~130gがベスト。もちろん潮が速かったりすれば、その速度でしっかりと棚が取れる重さに調整する。
フック&マテリアル
サクラマスジギングでダントツに人気と信頼性が高いのが、「エゾハチ/ささらさる」シリーズのフック。私も何度か使用させてもらったが、フック自体に軽さがありながら硬さを持つ、貫通性の高いフック。北海道エリアで最も使われているアシストフックだと言える。他には、スロージギング用で販売されているアシストフックを代用。オーナーばりのカルティバなら2/0~4/0サイズ(全社統一号数でない)が良いだろう。また、ジグのフロント、リアとの装着は、サクラマスジギングの捕食体制が、エサを追う場面と威嚇(いかく)攻撃と分かれるため、最初はフロント(頭)、リア(お尻)ともに付けておく方が無難だろう。ちなみにこの文章を読んで下さっている対象を初心者として解説しているので、釣り慣れたアングラーは自分のスタイルに合わせてセレクトすれば良いと思う。またスプリットリングサイズは、小さめを選択するのが良い。サイズ的には#1~3程度で十分だろう。

多くの地元アングラーが、愛用しているアシストフックがこれ。フックが軽く、硬さがあり、貫通性能も高い。長さバリエーションも多いので、様々なジグに合わせやすい。

私が愛用しているのは、オーナーばりのカルティバのシワリ、ホールド、速掛。2/0~4/0サイズをセレクトしている。


フックは、前後に装着するのが一般的。フォールでも巻きでもフッキングに繋がる設定。

巻きでアタリが連発するような状況なら、フロントにフックを装着するだけでも良い。どんなアタリ方をするのか、周りのアングラーの釣果も見て把握することが、自身の釣果にも繋がる。
サクラマスジギングの狙い方
最初にお伝えしておきたいのが、エリアによってサクラマス釣りのライセンス制度を設けられ、釣果リミットを組んでいるエリアがあるということ。地域によって違うので、その辺りは乗船時に確認しておきたい。
さて実釣では、ポイントに到着したら船長からの指示棚(水深)を中心に狙っていく。指示棚から前後20mを意識してしゃくっていくのが基本となる。テクニックとしては、しゃくるスピードなどがあるが、まずはワンピッチアクションで探る。これは、ジグが指示棚でしっかり動いているかの確認である。そしてそれが分かってから、指示棚前後20mを丁寧に攻めていく。サクラマスは根や何かに付いているのではなく、ベイト(エサ)を追って層を回遊している。サクラマスが回遊する棚(層)に、いかにジグを置けるか、が大切。狙う指示を越えた深さになれば、タラやホッケ、カレイなどが反応してしまう。ただそれらの魚と混成して回遊する場合も多いので、常にジグアクションは丁寧に行うことが必要だ。
ヒットパターンとしては、しゃくるスピードにインパクトを入れリアクションでサクラマスを寄せ、ジグのフォール時に攻撃してくる感じが多い。ジグを引いている時のバイトは、よほど活性が高い時以外は少ない。しゃくり上げ、アピールして少しジグへのテンションを抑えた時のバイト(ヒット)が多い。ジグを持ち上げる、次にロッドを下げたタイミングでラインの張りが緩む場面でジグが少し後進、そして止まる。このタイミングがヒットパターンになる。初心者のアングラーは、慣れていそうなアングラーのロッドワークを真似してみるのも大切だ。
また、サクラマスの捕食パターンは大きく分けて二つある。本当にベイト(エサ)を追っている時のパターン。もう一つは、目の前(魚眼)エリアで反射的な動きをしている物への戯れ、威嚇(いかく)パターン。前者はいわゆる一般的な捕食だが、後者はサクラマス特有の攻撃。魚類は魚を捕食する際、ボディー(尾鰭なども含む)で叩いて攻撃するか、口で攻撃する。経験上、太陽がまだ低い時間帯は、エサを追ってジグに当たる事が多いが、太陽光が高い位置から指す時間帯になると、威嚇(いかく)攻撃パターンに変わることが多い。戯れてくる、と言う表現もこれに当てはまる。こうしたサクラマスの行動を把握する事で、狙いやすくなる。
そしてサクラマスは、ヒットしたらよく走る。外道魚になるホッケやカレイとは、暴れ方が大きく違う。この時、慌てて寄せようとすると、身切れが起こるので注意。サクラマスの口頭部周辺は柔らかく、強引な寄せ(ファイト)は向かない。ロッドを立て過ぎず、無理しない様なファイトで対応するのがベストだ。

サクラマスジギングは、回遊している棚を重点的に攻めることが大切。そのため、同船者と情報交換しつつ、釣れた人、アタった人からの情報をしっかりと把握しておくことが重要だ。フォール中も気を抜けない。

ヒットしてから、サクラマスは走る。口が柔らかいため、慎重に寄せてきたい。

回遊が訪れると、船中でパタパタとヒットすることもある。チャンスタイムを逃さないようにしたい。

ベイトとなるオオナゴ。このサイズを喰っていることもある。

お馴染みの外道、ホッケ。次々と釣れてくることも多い。
平松流のマストパターン
本州から冬の北海道へ出向いてのサクラマスジギングの最初は、まず寒さにやられた思い出があります。まずは寒さ対策からのスタート。釣れるジグは何か? タックルはどのようなものが良いのか? ということよりも大切に感じたのが、指先の保温確保だった。私としてはジギングをする際に分厚いグローブは使いたく無い。しかし、手のひらを寒さから守るためにはグローブが必要。ただ、サクラマスを釣り、手持ちで写真などを撮ってもらった後の濡れたグローブの対応も考えなくてはならない。そこでサクラマス狙いの時の私のマストパターンとなったのが、薄いグローブを何枚も準備しておき、濡れたら直ぐにグローブを変えるというもの。このようなことを最初に感じ、今でも重要事項だと思っている。
ジグのカラーなど、ギア的な選択も現場に入れば様々なことが出てくるが、私はサクラマスの捕食パターンを知ってからは、カラーで悩むことは少なくなった。ジグカラーなら、裏面は反射版の役目をするフラッシング効果の高いミラー系が施されたもの。表面は「好み」だと大雑把ではあるが感じている。落としていく、しゃくるタイミングでミラー面がサクラマスにアピールし、サクラマスの興味を惹かせる。寄ったサクラマスを捕食パターンで狙うのか、威嚇(いかく)パターンで狙うのかが、このゲームの面白いところ。それを頭に入れて楽しんでもらいたい。


集中力を切らさずに探っていくためにも、防寒対策はしっかりと用意しておきたい。

地元の人は寒くないと言う日でも、関東の人間からすると寒い。特に冷えるのが指先。グローブはしっかりとしたものを用意するか、替えを用意しておく。



カラーは好みのもので良いが、アピールのあるミラー系、シルエットがはっきり出るカラー、濁りの中で気づかせるチャートなど、数種類のカラーを用意しておく。
北海道サクラマスジギングは、私にとって非常にゲーム性の高い釣りだと感じている。ちなみにサクラマスジギングを覚えた当初から、河川のトラウトゲームにも没頭するようになった。これは、海で狙うサクラマスジギングで、マス類の行動を知りたかったからだ。
オフショアで狙うマス類と河川で狙うマス類の本能は変わらない。バーチカル(垂直)に組み立てるオフショア、フラット(平面)で探るフレッシュ、ともにマス類をどのように狙うかは、「エサを食べるのか」「攻撃的行動なのか」を考え、実践して来た。秋に湖で狙うヒメマス(チップ)。深場に生息していたヒメマスは産卵を控えて湖岸に寄ってくる。水色が澄んだ場所で、ヒメマスをいかに寄せて攻撃させるか。これがオフショアゲームで狙うサクラマスジギングでも、全く同じ要領だと気付き、ゲーム性を高く感じているのだ。海でマスを狙いたい。だからマス本来の生息域でマスを学ぶ。こんなスタイルから始まった私のサクラマスジギング。これからがオホーツク海エリアの本格的なシーズンイン。2023年は、オホーツク海を中心にサクラマスジギングを楽しみたいと今からワクワクしている。